6月5日の記事で地下鉄・私鉄事業者が1960年代以降、運賃制度として対キロ区間制を採用したと書いた。地下鉄が均一運賃から対キロ区間制に移行したのは、路線網の拡充によって均一運賃では対応できなくなったためである。それではなぜ当時主流だった対キロ制、区間制を採用しなかったのか。また、その後多くの私鉄が対キロ制、区間制から対キロ区間制に移行したのはなぜか。結論を先に言えば、乗車距離に比例しないコストを運賃に転嫁しにくい対キロ制と短距離区間の運賃が長距離区間よりも高い逆転現象が生じる区間制の弱点を対キロ区間制が解決できるからだろう。
旅客輸送のコストは、出札や改札など乗車距離に比例しないコスト(ターミナルコスト)がある。このため、対キロ制は、乗車距離が長くなればキロ当たりの賃率が低下する遠距離逓制を採用する。JRの運賃は、国鉄時代の運賃体系を踏襲し、300キロまで同一賃率を採用しているため、都市圏内の短・中距離区間ではこの遠距離逓減効果が働かない。これに対し対キロ制を採用した大手私鉄は、対キロ賃率をきめ細かく設定した。例えば、東急1928年1月から1946年3月まで、最初の3キロまで2.3銭/キロ、以降3キロごとに1厘(0.1銭)逓減する遠距離逓減賃率を採用していた。また小田急は、対キロ区間制への移行直前まで、30-40キロ前後で2段階の対キロ賃率を設定していた。
事業者にとって対キロ制の問題点は、運賃区分が小さく、多くの区間の乗車券を常備する必要があったことである。このため、国鉄は、1966年3月5日の運賃制度改定でキロ地帯制を採用した。従来の10円刻みの運賃から、一定の刻みのキロ帯を設定し、キロ帯ごとに同一運賃とする制度である。51キロから100キロまでは5キロ刻み、101キロから400キロまでは10キロ刻み、401キロ以上は20キロ刻みとし、その中央値の営業キロに対キロ賃率を乗じて運賃を算出することとした。69年5月10日からは、6キロから50キロまで5キロ刻み、101キロから500キロまでは20キロ刻み、501キロ以上は40キロ刻みと、キロ刻みを粗くした。また、関西私鉄が区間制から対キロ区間制に移行時した1974年7月20日の運賃改定時に、関東の大手私鉄が国鉄と同様のキロ地帯制(東武は、5〜50キロを5キロごと、51〜100キロを10キロごと、100キロ以上を20キロごとに区分。京急は5キロごとに区分)を採用した。対キロ区間制への移行に先行して、対キロ制のまま、同一運賃が適用されるキロ帯を拡大したのである。
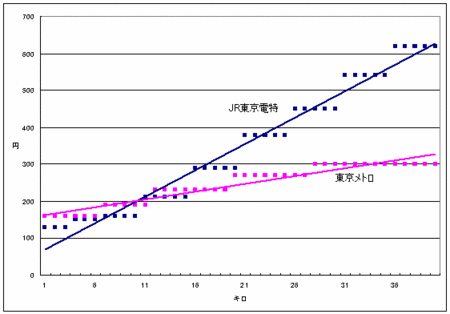 その結果、対キロ賃率に乗車区間の営業キロを乗じて運賃を算出する対キロ制も、実際には対キロ区間制と同様、一定の間隔でキロを刻み、運賃は階段状に上昇することになった。グラフは、対キロ制のJR(電車特定区間)と対キロ区間制の東京メトロの運賃上昇カーブを比較したものである*1。JRも国鉄時代の1974年10月1日の運賃改定で営業キロが10キロまでの初乗り運賃を賃率によらず特定したため、線形回帰した近似直線は原点を通る一次関数にはならない。それでも、対キロ区間制が初乗り運賃の固定額+距離比例額という遠距離逓減運賃になっているのと比べると、対キロ比例的である。
その結果、対キロ賃率に乗車区間の営業キロを乗じて運賃を算出する対キロ制も、実際には対キロ区間制と同様、一定の間隔でキロを刻み、運賃は階段状に上昇することになった。グラフは、対キロ制のJR(電車特定区間)と対キロ区間制の東京メトロの運賃上昇カーブを比較したものである*1。JRも国鉄時代の1974年10月1日の運賃改定で営業キロが10キロまでの初乗り運賃を賃率によらず特定したため、線形回帰した近似直線は原点を通る一次関数にはならない。それでも、対キロ区間制が初乗り運賃の固定額+距離比例額という遠距離逓減運賃になっているのと比べると、対キロ比例的である。
キロ地帯制を併用した対キロ制運賃は、目的地まで乗車券を購入するよりも区間を分割して乗車券を購入するほうが運賃が安くなる矛盾を内包している。たとえば26〜30キロ帯の運賃は、中央値の28キロで計算されるから、11〜15キロ帯(13キロで計算)の2区間に分割できれば、26キロ (13キロ x 2)の運賃でよいことになる。実際に本州幹線の26〜30キロの運賃は480円であり、11〜15キロの乗車券(230円)2枚分の460円よりも高い。抜本的な対策は、国鉄・JRが伝統的に採用してきた対キロ制運賃をやめて、対キロ区間制を採用する*2ことだが、キロ帯区分を小刻みにすれば、運賃の逆転現象は減少する。コンピュータによる発券、ICカード乗車券の普及により、乗車券の常備という制約がなくなったにもかかわらず、10キロ超のキロ刻みは1974年10月から変更がない。
現在も対キロ制を採用しているのは、JR6社のほか青い森鉄道、IGRいわて銀河鉄道、仙台空港鉄道、ひたちなか海浜鉄道、鹿島臨海鉄道、箱根登山鉄道(鉄道線)、立山黒部貫光、アルピコ交通、上田電鉄、しなの鉄道、大井川鐵道、遠州鉄道、島原鉄道、熊本電気鉄道である。このうち、JRと青い森鉄道、IGRいわて銀河鉄道を除く各社は、初乗り区間を除き*3キロ地帯制を併用せず、1キロ刻みで運賃を定めている。
区間制から対キロ区間制への移行については、別稿で。